[薪ストーブ] - 薪の種類編 -
2017/03/10
薪の種類とは木の種類とも言えるので、当然沢山あります。
実際に使ってみたことがある薪の話しか出来ませんが、それでも薪はそれぞれ個性的だし、中には注意しなくてはいけないものもありました。
今回は薪の種類についてまとめてみようと思います。
樹木には大きく分けて、「針葉樹」と「広葉樹」があります。
薪にするなら断然、「広葉樹」が喜ばれます。ホームセンターで売っているような高級な薪は、まず「広葉樹」だと思って間違いないです。
広葉樹が良いというよりは、針葉樹の薪が扱いづらいといった方が良いかもしれません。
何故「針葉樹」は薪に向かないと言われているのか?
「針葉樹」は成長が早いので、その分身が詰まっていないのです。だから薪にしても直ぐに燃え尽きてしまうのです。
また、松などは顕著ですが、ヤニを多分に含んでいるので、炉内が高温となり、ストーブを痛めると言われています。
さらに松ヤニは、煙突内に付着するとその部分が高温となり、煙突火災の原因となるのだと教わったことがあります。
赤松の薪は、暖をとるストーブよりも、焼き物の釜に向いているようです。
ただ、人が変われば意見も変わるようで、赤松だったら2年から3年乾燥させればヤニが抜け、薪にしても良いという人がいます。
杉や桧だって早く燃え尽きてしまうだけでどんどん継ぎ足していけば良いだけだとも言っていました。
また、針葉樹、広葉樹を混ぜて燃やせば大丈夫だと言う人もいました。
いろいろ意見があることは分かりましたが、結局、自分で試してみないことには判断はつかないのかもしれません。
僕が買った安い薪ストーブ(※確か1万円前半)だったら、そんな実験をするには最適かもしれません。
普段使っている薪の[特徴]を独断と偏見で!
【広葉樹】
「ナラ」
クヌギと並び高級薪として有名。火の着きはあまり良いとは思えませんが、一度着火すれば安定した炎で長時間燃え続けてくれました。
薪として人気が高いため、非常に高価です。ホームセンターで売っている薪はだいたいこれかクヌギだと思います。

「桜」
始めの頃は、桜を薪にするなんて本当に贅沢だと思いました。
暖かくて火持ちもよいと思います。
桜を燃やしていると思うだけで、ほんのり甘く香る気がします。
※スモーク(燻製)に使う木なので当然かもしれません。
サクラの木をチェーンソーで切った時に出るチップは、スモーク(燻製)で使えます。
※チェーンソーオイルが混ざるので良くないという意見もあります。

「クリ」
こちらも山梨の山林では良く見かける広葉樹です。
温度も火持ちも悪くはありませんが、乾燥期間が短いとパチパチとはぜるので注意が必要です。
はぜた火種が空気の取り入れ口から飛び出ることもありえるので、火事に注意です。
新たに薪をくべようと、薪ストーブの扉を開ける際にも同様に危険です。

「クルミ」
こちらも非常にポピュラーです。
クリとは違い、はぜることもないし、入手の安易さを考えると、かなり優秀だと思っています。
また、薪割りに関しても、素直にパカっと割れてくれるのでとても楽です。

「ハリエンジュ(ニセアカシア)」
入手しやすく火持ちが良いこの薪が僕は大好きです。
水辺に多く分布する広葉樹です。その為、河川の伐木で切られる木の多くはこのハリエンジュとなります。
広葉樹の割に成長が早く、しっかりと身が詰まっていてズッシリと重いです。
重いということは、それだけ火持ちがよいということです。
伐木されたばかりの頃は、ハリエンジュ特有の甘い香りがキツく感じますが、時間経過とともに気にならなくなります。
注意点は水辺の木だからか、他の薪よりも乾燥期間を長くする必要があるようです。
僕の薪棚は日差しも良く、風通しも良かった為か、一年程度で燃やしてみましたが、問題は感じませんでした。
ハリエンジュは最低でも一年半は乾燥させるべきだと言う人もいます。参考までに。

「モミジ・カエデ」
驚くほど火の着きが良く、高温になります。
焚付けに重宝します。

※参考※
「クヌギ」
ナラ同様クヌギはホームセンターでも売っている高級薪の代名詞ですが、僕にはあまり縁がなく、使ったことがあるのは半分腐ってしまったような誰も見向きもしない状態のものだけなので、参考にはなりません。
因みにその半分腐ったようなクヌギは火の着きも最悪で、やっと着いたと思ったら直ぐに燃え尽きてしまいました。
当たり前ですね。いつかまともなクヌギをお金を出さずに燃やしてみたいです。
「ケヤキ」
ケヤキの煙は目に悪いから使ってはいけないという人がいたので、参考までに書きました。僕はまだ燃やしたことがありません。
【針葉樹】
「ヒノキ・スギ」
この二つは違いを感じることが出来なかったので一緒に書いてしまいます。
着火は良好、良く乾燥していれば直ぐにストーブが温まりました。
確かに燃えるスピードは広葉樹の薪に比べ早いですが、太く割れば十分長い時間燃え続けてくれると思っています。
焚き付け時には重宝するし、他の広葉樹と一緒に燃やせば何の問題も無いと感じています。

「赤松」
乾燥期間は1年しか経っていないのですが、興味があって燃やしてみました。
細く割った赤松を焚き付けに使ったのですが、火の着きは最高レベルで、驚いたのはその温度です。調子に乗って沢山入れていたら怖くなるほど温度が上がり、「チンチンになる」という表現がぴったりに思える状態になりました。
これも他の広葉樹と混ぜて燃やせば大丈夫ではないかと思うのですが、その真価は乾燥期間が2年を経過する来シーズンに分かると思います。
※2016年6月追記:乾燥期間が2年を経過した赤松を、暖を取る為の薪として使いました。
使い方は、出来るだけ広葉樹と一緒に燃やすといった程度で、それほど慎重に扱うことなく、普段使いの薪の一種類として使えました。
原因が赤松のヤニとは断定出来ないものの、煙突の掃除回数は若干増えました。

番外編
「リンゴ」
僕がいつか使ってみたいと思っている薪です。
燃やすととても良い香りがするらしいのです。
因みに、アメリカのホワイトハウスでは、大切なお客さんを迎える時、ストーブではこのリンゴの薪を燃やすらしいです。
これはきっと、勝負薪なのでしょう。
最後に
自分の土地で伐木したものや、譲渡会で貰った木の中には名前の分からないものもあります。
不明な木でも、何度か燃やしているうちに、素材の色や重さ、表皮の感じで覚えてしまいます。
直ぐに燃え尽きてしまったり、火の着きが悪かったりと様々ですが、名前が分からないので、掲載を控えました。
名前の分からない薪には勝手に命名して判別しています。
色や見た目の模様なんかで、カッパだとか、カモフラだとか、見た目は派手だけど持つと軽くて詰まっていない薪には◯◯とかです。
命名作業は誰かの前で言ってしまわない限り、なかなか面白いです。

「参考:一日に使う薪の量」

もっと天井の低い小屋にしておけば良かったと思うのはこんな時です。
薪ストーブを使ったレシピなど、書きたいことはまだまだ沢山ありますが、次回、ストーブの設置や薪割りについて触れたらひとまず終わりにします。
[関連記事]
 | 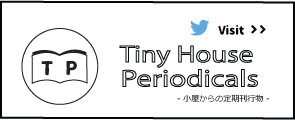 |


